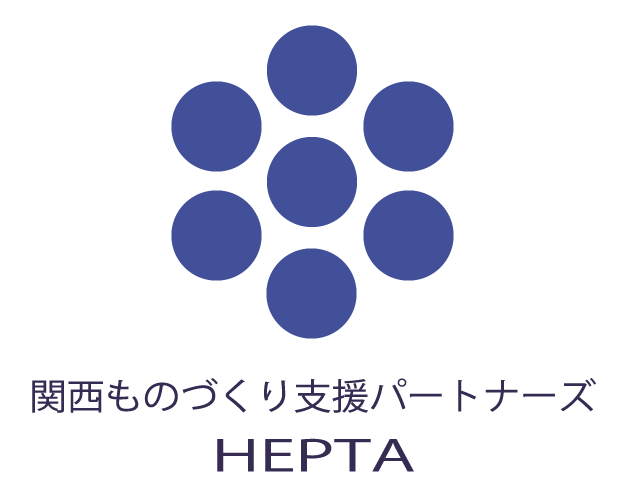こんんちは、ものづくり支援パートナーの上村拓也です。
製造現場において、「もっと効率よくできないか?」「ムダな作業が多い気がする…」と感じたことはありませんか?
そんなときに活用できるシンプルで効果的な改善のフレームワークが ECRSの原則 です。
ECRSとは、以下の4つの頭文字を取った改善の考え方です。
- E:Eliminate(排除)
- C:Combine(結合)
- R:Rearrange(入れ替え)
- S:Simplify(簡素化)
この順番もポイント。E → C → R → Sの順で検討することで、より本質的な改善につながります。それでは、それぞれの内容と現場での活用例をご紹介します。
1.Eliminate(排除)|本当に必要か?を疑う
最も効果の大きい改善は、そもそもやめることです。
「この作業、なぜやっているの?」と問い直してみましょう。
現場例:
検査工程が二重になっていた → 1つに集約しても品質に影響なし
日報の紙記入 → 実は誰も読んでいない → データ入力のみに切り替え
一度ゼロベースで見直すことが、ムダの発見につながります。
2.Combine(結合)|まとめられないか?
作業や工程を一緒にできないか?を検討します。
現場例:
部品を取りに行く作業と、次工程への引き渡し作業を1回で実施
複数の帳票を1枚のチェックリストに統合
人やモノの移動回数、手間が減ることで大きな効率化に。
3.Rearrange(入れ替え)|順番やレイアウトを見直す
工程や作業の順番や配置を変えるだけでも改善は可能です。
現場例:
部品棚をラインのすぐ横に移動 → 移動時間が半減
重いものを作業後半に扱っていた → 最初に処理することで負担軽減
流れをスムーズにすることは、安全性や生産性にも直結します。
4.Simplify(簡素化)|もっと簡単にできないか?
最後に、「もっとシンプルにできないか?」を考えます。
これは作業手順や道具の改善など、工夫の余地を探す段階です。
現場例:
ボルトの締め付けをトルクレンチで簡単に
治具を自作して部品の位置決めを一発でできるように
コストをかけなくても、小さな改善の積み重ねが大きな成果になります。
なぜECRSは中小製造業に向いているのか?
中小企業の現場は、人の知恵と工夫で支えられていることが多いです。
だからこそ、「ゼロから改善できる」ECRSは現場改善にぴったり。
大がかりな投資やIT化ではなく、すぐに現場で実践できるヒントが満載なのです。
最後に|「ないじゅかの原則」で覚えよう!
ECRSと英語の頭文字だと覚えにくい!
そのような人には、次のようにも覚え方もお伝えしておきます。
「ないじゅかの原則」= な・い・じゅ・か
な:なくせないか?=E
い:一緒に出来ないか?=C
じゅ:順番を変えられないか?=R
か:簡単にできないか?=S
現場の誰もがすぐに使える「問いのフレーム」として、この形は非常に強力です。
ぜひ日々の仕事の中で、「これ、ないじゅかできないか?」と声をかけ合ってみてください。
小さな改善が積み重なれば、現場はどんどん良くなります!