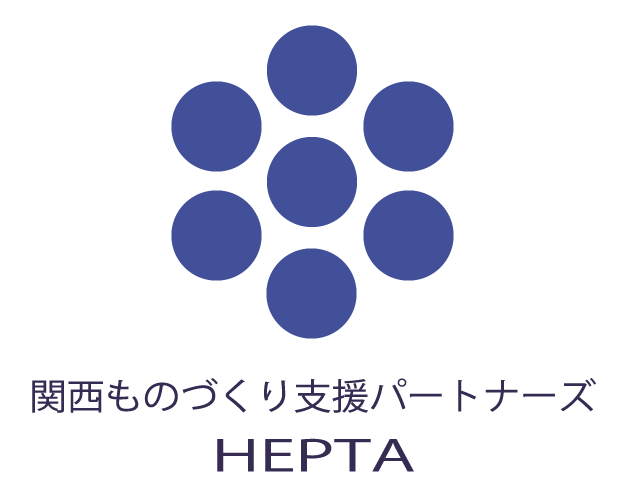ものづくり支援パートナーズの上村です。
中小製造業にとって自社では対応できない工事業者は欠かせないパートナーです。
しかし、特に小規模な工事業者に依存していると「思わぬリスク」に直面することがあります。今回は、後継者不足や一社依存のリスクを避けつつ、安定的にコストを抑えるための外注戦略を考えてみます。
小規模業者に依存する2つのリスク
1. 後継者不足による廃業リスク
熟練職人に支えられた小規模業者や個人事業主は、技術力も高くコストも安いのが魅力です。
しかし「後継者がいない」「高齢化が進んでいる」といった背景から、突然廃業になる可能性があります。これまで頼っていた工事が急に止まってしまうのは大きなリスクです。
2. 圧倒的な低価格ゆえの一社依存
熟練職人は効率が高く、他社の見積りよりも圧倒的に安い価格を提示することがあります。
その結果「相見積もりを取っても他社が太刀打ちできない」という状態になり、複数購買の仕組みが機能しなくなってしまうのです。
そして圧倒的な価格と品質で対応いただける工事業者がなくなってしまい、急に他社に発注をすると価格も品質も悪くなってしまうリスクがあります。
規模の大きな業者に発注するメリット・デメリット
こうしたリスクを避ける一つの方法は、一定規模の業者へ発注シフトすることです。
- メリット
- 廃業リスクが低く、安定取引が可能
- 人員が多く、急な案件にも対応可能
- 品質や安全基準がマニュアル化されている
- デメリット
- 小規模業者より単価が高い
- 柔軟さや職人の裁量による工夫は減りがち
安定性は手に入りますが、その分コストが上がる点が課題です。
内製化で補うという選択肢
コスト上昇を吸収するためには、内製化の工夫が有効です。
とは言いながらも中小企業・小規模事業者が内製化するにはコストがかかります。
また個人事業主でされている職人さんは組織勤めになるよりも収入が多い可能性が高く、わざわざ組織で勤めようとされないかもしれません。
他社よりも良い案件で採用をする。また1から社内でその工事や工程を担ってもらうというところで責任や仕事の範囲が大きく、自身で作り上げていけるというやりがいを訴求するのも方法かもしれません。
または引退された職人さんに技術顧問として入っていただき、そのノウハウを教えてもらうという採用の方法も1つの案です。
コスト上昇を抑える4つの工夫
規模の大きな業者を選ぶと単価は上がりますが、以下の工夫で実質的なコストダウンが可能です。
- 仕様の明確化・標準化
曖昧な依頼は「安全マージン」で高額見積につながる。標準仕様書を用意し、余計な上乗せを防ぐ。 - 工数削減による効率化
- 工事写真や日報をクラウド共有
- 資材搬入や片付けを自社で担当し、施工時間を短縮
- 長期的コストで判断する
小規模業者に依存して突然工事がストップすれば、緊急対応で結果的に割高になる。大手に頼んで安定を得ること自体が、長期的にはコスト削減につながる。
まとめ
小規模業者に依存することは「低コスト」と引き換えに「高リスク」を抱えることでもあります。
そのリスクを回避するために、一定規模の業者への発注と内製化を組み合わせ、さらに「仕様明確化」「デジタル活用」でコスト上昇を吸収していくことが重要です。
短期的な安さではなく、長期的な安定性とトータルコストを基準に外注戦略を見直すこと。
これが、中小企業が外注費とリスクを両立して管理するための鍵だといえるでしょう。