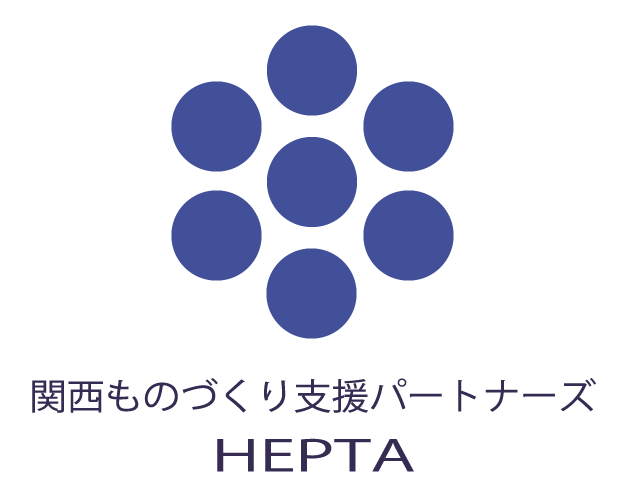こんにちは。
ものづくり支援パートナーズの上村です。
購買や調達の現場でよく聞くのが「相見積もりを取ってコストを下げる」という手法です。
もちろん複数の見積もりを比べること自体は有効です。しかし、これだけに頼ると本当の意味での“賢い取引”にはつながりません。今回は、中小企業の経営者にこそ考えていただきたい「相見積もりの限界」と「一歩先の取引術」についてお伝えします。
値段だけでは測れない「真のコスト」
見積書に書かれた単価だけを比較すると、一番安い会社に発注するのが正解に見えます。
しかし実際には、その後の納期遅延や品質不良、対応の遅さなどで思わぬコストが発生することがあります。結果的に「安いと思ったのに高くついた」ということは珍しくありません。価格は大事ですが、それだけで判断するのは危険です。
ポイントは「総合力」で比較する
賢い取引を考えるなら、次のような視点も加えて仕入れ先を評価しましょう。
- 納期遵守率:遅れが少ないかどうか。生産計画に直結します。
- 品質安定性:検品で不良が多ければ、安さの意味はありません。
- 柔軟対応力:急な追加や仕様変更に応じてくれるか。
- コミュニケーション:担当者が信頼できるかどうか。
これらは数字で見えにくいですが、実際に経営に効いてくる重要な要素です。
サプライヤーと「関係性」を育てる
また、中小企業の場合はサプライヤーとの距離感も大きな武器になります。発注先を“ただの取引先”として見るのではなく、パートナーとして関係性を育てることが大切です。例えば、こちらの状況や方針を共有しておくと、相手も協力的になりやすくなります。「実はこの部材、来期は数量が増える予定なんです」と一言添えるだけでも、相手の姿勢は変わってきます。
「比較」から「選択と育成」へ
相見積もりは“比較の出発点”に過ぎません。その先で重要なのは「誰と長く付き合い、どう育てていくか」という視点です。値段で競わせて短期的に削るのではなく、信頼できるサプライヤーと一緒に成長する方が、結果的にコストも利益も安定します。
まとめ
相見積もりは調達の基本ですが、それだけでは弱い武器です。値段以外の要素に目を向け、サプライヤーを「選び、育てる」ことで初めて、経営を強くする購買が実現します。経営者にとって調達は単なるコスト削減活動ではなく、“会社の未来をともにつくる戦略”であると捉えてみてください。