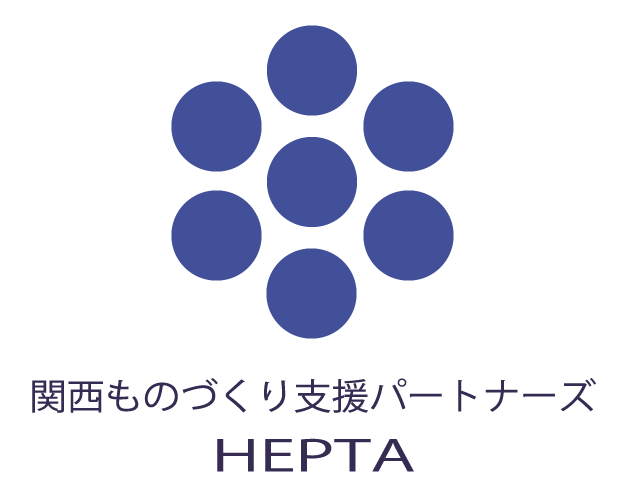なぜ「整理」から始めるのか
「5S活動を始めよう」と決意したものの、何から手をつければいいのか悩んでいませんか。工場内を見渡せば、工具は散乱し、使わない治具が棚を占領し、「いつか使うかも」という金型が通路脇に積まれている。これは多くの製造現場でよく見られる光景です。
このような状況で、いきなり「整頓」しようとしても、不要なモノまで整然と並べることになりかねません。「清掃」に力を入れても、翌日にはまた元通り。5S活動が形骸化してしまう最大の原因は、実は「整理」を疎かにしたことにあるのです。
整理とは何か――よくある誤解を解く
整理とは「必要なモノと不要なモノを分け、不要なモノを処分すること」です。ここで注意したいのは、整頓(必要なモノを使いやすく配置すること)や清掃(きれいにすること)との違いです。
例えば、あるプレス工場のA班長は当初、工具を種類別にきれいに並べることが「整理」だと思っていました。しかし、よく見ると、並んでいる30本のスパナのうち、実際に使っているのは10本だけ。残り20本は「予備」という名目で5年間一度も使われていませんでした。これらを処分して初めて、真の「整理」が始まったのです。
整理を第一歩にすべき理由
理由1:他の4Sの土台を作る
整理なくして他の4Sは成立しません。ある電子部品工場では、組立ラインの工具棚に40種類以上の工具が詰め込まれていました。作業者は「欲しい工具がどこにあるかわからない」と訴え、整頓の必要性を感じていました。
そこで、整理を実施した結果、実際に使用する工具は12種類だけだと判明。不要な28種類を処分したことで、棚のスペースは3分の1に。その後の整頓作業は驚くほどスムーズに進み、工具の取り出し時間は平均40秒から8秒へと大幅に短縮されました。
理由2:隠れた問題を可視化する
整理の過程で、現場の真の課題が次々と明らかになります。ある金属加工工場では、倉庫の整理中に5年前の規格品が大量に見つかりました。調査の結果、発注システムの不備が原因で過剰在庫が発生していたことが判明。整理をきっかけに、在庫管理システムの改善につながったのです。
別の事例では、機械周辺の「とりあえず置き場」を整理したところ、同じ部品が3カ所に分散して保管されていることが発覚。これは部署間のコミュニケーション不足が原因でした。整理は単なる片付けではなく、組織の問題を診断するツールでもあるのです。
理由3:比較的容易で成果が出やすい
整理は「必要か不要か」という二択で判断できるため、他の4Sと比較して実行のハードルが低いのが特徴です。さらに、成果が目に見えやすいため、チームのモチベーション向上につながります。
樹脂成形工場のBチームは、まず「1年間使用しなかったモノは不要」という明確な基準を設定しました。すると、わずか2週間で作業エリアの床面積を15%拡大することに成功。この「勝利体験」がチームの自信となり、次の整頓フェーズへの推進力になりました。
理由4:コスト削減効果が即座に現れる
整理によって不要なモノが減ると、保管スペースの削減、探索時間の短縮、在庫管理コストの低減など、具体的な経済効果が生まれます。自動車部品メーカーのC工場では、整理によって倉庫の20%のスペースが空き、外部倉庫の賃借契約を解除できました。年間約150万円のコスト削減です。
整理の具体的な実施ステップ
ステップ1:小さなエリアから始める
いきなり工場全体に取り組むのは禁物です。「この作業台だけ」「この棚1つだけ」といった、15分程度で完了できる小さなエリアから始めましょう。成功体験を積み重ねることが重要です。
ステップ2:判定基準を明確にする
「いつか使うかも」という心理的なハードルを下げるため、客観的な基準が必要です。おすすめは以下の3分類です:
- 頻繁に使用(週1回以上)→ 作業場に保管
- 時々使用(月1回~週1回)→ 近くの保管場所へ
- ほとんど使わない(月1回未満)→ 処分または集中保管
ある精密機械工場では、判断に迷うモノに赤札を貼り、1ヶ月間「保留エリア」に置く「赤札作戦」を実施。この期間に使用されなかったモノは処分対象としました。この方法により、「もしかしたら」という心理的抵抗を和らげることができました。
ステップ3:チーム全員で実行する
整理は一人でやるものではありません。D工場では、毎週金曜午後の30分を「整理タイム」として、チーム全員で実施。ベテラン作業者Eさんが「これは20年前の金型用の部品だ。もう使わないよ」と判断できたように、現場の知恵を集めることが重要です。
実装時の注意点と工夫
「捨てられない」心理への対処
「高価だった」「まだ使える」という心理的な抵抗は自然なことです。そんな時は、写真を撮って記録を残す方法が有効です。また、他部署で使える可能性があるモノは「譲渡リスト」を作成し、社内SNSで共有する工場もあります。
モチベーション維持の工夫
ビフォー・アフターの写真を掲示板に貼り出す、削減できたスペースを床に図示する、削減コストを見える化するなど、成果を可視化することが継続の鍵です。F工場では、整理で空いたスペースに「休憩用ベンチ」を設置したところ、「次はもっと広げよう」という機運が高まりました。
次のステップへの道筋
整理が完了すれば、次の整頓がずっと楽になります。必要なモノだけになった状態で配置を考え、表示を工夫し、取り出しやすい仕組みを作る。これが本来の整頓です。
そして清掃へ。モノが減れば清掃時間も短縮されます。ある工場では、整理後に清掃時間が半分になったと報告されています。
「整理は終わりではなく、始まりです。」小さな一歩から、現場は確実に変わっていきます。まずは明日、自分のデスク周りの「整理」から始めてみませんか。その小さな成功体験が、工場全体を変える大きなうねりになるはずです。