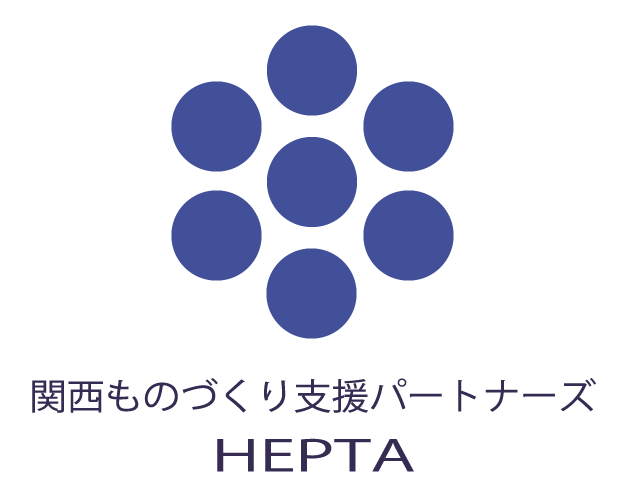みなさん、こんにちは。ものづくり支援パートナーズの内藤です。
最近、マスコミやネット情報では異物混入の報道が絶えません。
飲食店で提供する料理に動物や昆虫が入っていた。学校給食に金属片が混入していた。スーパーで購入した乳製品に線状の金属が見つかった。食品を扱う企業、特に食品工場にとって異物混入は最も注意しなければならない管理項目です。
異物混入という企業のミスはSNSによって拡散され、報道機関によって多くの人に伝わっていきます。その結果、顧客からの信用を失い、企業業績にも悪影響を与えてしまします。企業としては何としても異物混入などのミスを防がなければなりません。異物混入に限らず、数量間違い、出荷間違い、製品間違い、重量間違いなどのミスはヒューマンエラーに起因することがほとんどです。食品工場のように多くの人々が働く職場ではミスをゼロにすることが難しいのも事実ですが、ヒューマンエラー対策を継続的に続けることで、ミスを減らすことが可能なのです。
ヒューマンエラーとは、人間の判断や行動のミスなどによって、意図しない結果やトラブルが発生することです。
ヒューマンエラーは、年齢や経験に関係なく、若者から高齢者、一般社員から経営者まで誰でも起こす可能性があります。そしてどのような企業や現場でも無縁ではないのが実情です。
ヒューマンエラーの発生要因を見てみると、大きく分けて、個人に起因するものと環境に起因するものの2つがあります。
(1)個人に起因するもの
個人に起因するものとは、不注意・思い込み・スキル不足・手抜き・体調不良・疲労・イライラした心理状態 など、個人的な原因により発生するものです。
また、個人に起因するヒューマンエラーは、過失と故意によるものがあります。
①過失によるヒューマンエラー
注意が散漫になったため、意図しないうっかりミスをすることです。
・時間に追われるなど焦って見誤った
・疲れていて集中力を欠き違う操作をした
・勘違いして順番を間違えた
など。
②故意によるヒューマンエラー
やらなければいけないことを知っていたにも関わらず、手を抜いたりルールを守らなかったりすることです。
・時間がないので確認をしなかった
・見つからないだろうと思い必要な手順を省略した
・現物を見ないで管理表にチェックマークを記入した
など。
食品工場の製造現場ではこのように過失や故意によりヒューマンエラーが発生していますが、実際にヒアリングしてみると実はほとんどは故意によるものなのです。わかっているけれど「これくらいは大丈夫だろう」と多くの現場のメンバーは考えているのです。
(2)環境に起因するもの
環境に起因するものとは、作業内容が複雑、物理的な負担が大きい、設備や機器の不具合、コミュニケーションの取りにくい職場の雰囲気、危険な現場環境など、環境の不具合によりミスが発生することです。
一見、個人に起因するヒューマンエラーが多いように考えてしまいがちですが、なぜ?なぜ?を繰り返して原因を分析してみると、その多くは環境に起因するものに行き着くのです。個人的な不注意や疲労は、作業内容や過負荷、時間的な制約など、環境に起因することが根本原因であることが多いのです。
私の支援先である海産物加工業のA社では魚の加工を行っています。アジやサンマなどの近海魚を3枚におろし、魚の身から毛抜きを使って骨を取り除くのです。いわゆる骨なし魚です。ところが、A社では魚の身の中に小骨が混ざっているというクレームが時々発生します。これまでも同じようなクレームがあったため、魚の身に小骨が混ざらないように、作業者が目視と触感によって小骨の混入を防止してきました。「異物混入してはいけない」と繰り返し作業者に注意喚起し、作業の指導をおこなってきました。注意喚起を行った直後は収まるのですが、忘れたころに同じような小骨混入が発生することが繰り返されてきました。その都度、「もっと注意するように」と作業者個人に注意しますが、また繰り返されるのです。そのうち、「彼はやる気がない」「能力が不足している」など個人攻撃をし、職場の雰囲気がますます悪化していきます。
ヒューマンエラーを撲滅するためには、その根本原因は環境に起因するものであることを認識し、とことん改善することが重要です。個人に責任を転嫁するのではなく、本質的な改善が必要なのです。
A社では感覚センシングロボットを導入し、手作業による異物のチェック作業をロボットに置き換えました。
その結果、小骨による異物混入だけでなく、うろこやヒレなどの混入もゼロになりました。異物混入がなくなると、職場の雰囲気も改善され、報告・連絡・相談などのコミュニケーションも活発になりました。
B社は加工設備の設備チェックリストで保守・メンテナンスを行っていますが、時々設備が故障することがありました。よくよく作業者に確認すると、管理表にチェックマークは記入するけれど、実際には確認をしていなかったことが分かりました。典型的な個人に起因する故意のヒューマンエラーです。その作業者にヒアリングすると、管理表はあるが上長の確認がないために設備チェックが形骸化していたのです。やってもやらなくても注意されない状態です。そこで、管理表に上長の確認欄をつくり、毎日実際に設備のチェックをしたかを作業者に確認することにしました。作業者も自分事ととらえ、毎日もれなくチェックをするようになっただけでなく、設備に対する愛着もわき、設備清掃を積極的にするようになりました。
ヒューマンエラーの原因は、エラーを起こした本人にあると考えがちですが、使用する機器や職場環境、マネジメントなどの不備こそが根本原因なのです。
その原因を環境にあることを認識し、作業工程の改善、設備や機械への置き換え、作業環境の改善などを組み合わせ、継続的に改善を図っていきましょう。
以上