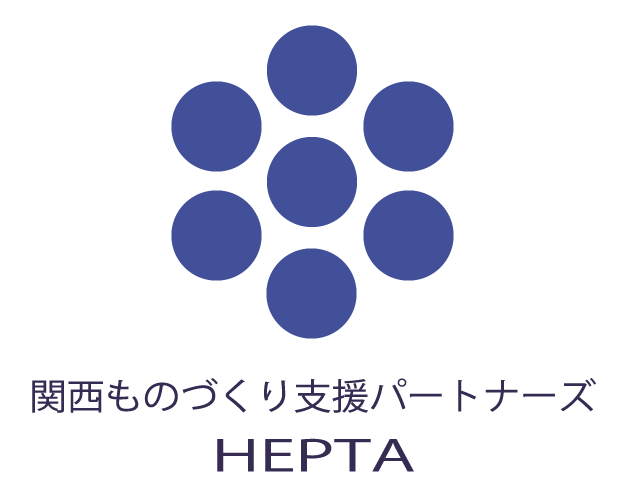ものづくり支援パートナーズの上村です。
今回は、「購買」という視点で意識することについての記事をお伝えさせていただきます。
■ はじめに|発注する側にも“関係性のデザイン”が求められる時代
サプライヤー(仕入先)との関係性は、かつてのような「選ぶ側・選ばれる側」という一方通行の構図から、「パートナーシップをどう築くか」という双方向の関係性へとシフトしています。
特に中堅〜中小企業においては、信頼できる取引先の確保と継続的な関係性の構築が、将来的な競争力を大きく左右します。価格や納期だけではなく、「一緒にものづくりができるか」「いざという時に踏ん張ってくれるか」といった“見えない信頼残高”がより重視されているのです。
その一方で、「無理な要求」や「理不尽な依頼」を繰り返す発注元は、優秀な仕入先からは徐々に敬遠されてしまいます。技術力があり信頼性の高い仕入先ほど、他にも取引先の選択肢があり、発注元を選ぶ立場にもなり得るからです。
発注者が陥りやすい罠として、「うちは発注側だから多少無理を言ってもいい」という意識が残っていることがあります。しかし、今の時代は、優秀な仕入先ほど“付き合う相手を選ぶ”ようになっています。むしろ、無理を押し付ける発注元からは静かに距離を取られ、気づいた時には「発注できる先が限られている」という状況に陥るリスクもあるのです。
本記事では、以下の視点から“選ばれる発注者”になるための視点と実践アクションを整理します。
仕入先は「下請け」ではなく「未来を一緒につくる仲間」
■ 大切な視点
「発注者≠上位者」
上下関係ではなく、プロジェクト成功のパートナーとしての目線で接することが必要です。
■具体アクション
●発注前に“背景情報”も共有(顧客事情・最終用途・工程全体像)
・顧客情報のシェア
→顧客情報のシェアは下請企業の従業員のモチベーションになることがあります。大手メーカーの仕事であれば、従業員の方々が「あの会社の製品の一部になっているのか」と社会への影響力を感じることができて、モチベーションの向上とともに品質や納期遵守の意識向上につながります。
・最終用途のシェア
→顧客情報と同じく最終用途が分かることによってモチベーション、品質意識が高まります。例えば、とあるドラマの話ではないですが部品が航空機やロケットに使われるという事が分かれば、なぜこんなに精度が求められるのか?といった事に対する理解が深まりますし、このような重要な部品に使われているのかというモチベーション向上にもつながります。
・工程全体像のシェア
→工程全体像を連絡することは仕入先にとっては信頼されているという証拠になり安心感につながります。ただ発注側として注意が必要なのは正式な注文書を発行せずに口答発注をすると下請法違反になります。これこそ「無理な要求」「理不尽な依頼」になります。あくまでも現状を事実ベースで伝えることが重要です。
また工程全体像を伝えることで仕入先側としては今後の人材配置の検討や他社の仕事受注の検討材料にもなります。仕入先は発注側の仕事の発注で大きく経営に左右されるような規模の会社も多くありますので、こういった情報は非常に助かります。
顧客情報や最終用途は口頭で伝えることでも大丈夫ですが、工程全体像はExcelやデータで伝えたり、クラウドを活用して情報をタイムリーに共有することも有効です。ただ顧客情報や最終用途については顧客との秘密保持契約の確認を行ったうえで社外に出しても良いものか否かの確認が必要です。
●トラブル時は責任追及より「共に原因を探る姿勢」
トラブル時にこそ仕入先との関係性が問われます。発注者という立場に胡坐をかいて責任追及を一方的におこなうと仕入先との信頼関係は崩れてしまいますし、零細企業であれば経営にも大きな影響を及ぼし、倒産のリスクもあります。
しかしここは精神論ではなく、しっかりと契約で決めておく必要があります。例えば以下のような取り決めをします。
・「納入して1年以内の不具合は無償対応、それ以降は有償対応とする」
・「ただし、明らかな仕入先の瑕疵である場合はその限りではない」
・「原因が不明な場合は発注側・仕入側が共同して問題解決に努めた上で別途協議をおこなう」
といったような内容です。
まずはその決められたルールには則った上で、不具合や納期遅れなどのトラブルの対策は共に考えます。仕入先はその分野の専門家であることが多いので仕入先の方が知識や経験が豊富な場合もありますが、自社の設計が図面や仕様書を書いた上で発注をしているような場合は、自社の設計や技術のスタッフを同席させて問題解決に努めることも有効です。
トラブルは仕入先との関係性を更に深める機会でもあると共に、仕入先の品質レベルと意識をあげるチャンスでもあります。一方的に責任を追及して丸投げするのではなく、共に成長する機会ととらえて関わることが大切です。
ただし、発注側が真摯に対応しているにもかかわらず、協力する姿勢がなかったり、姿勢はあるが明らかに技術力の低さが露呈してしまった場合は仕入先の見直しをおこなう必要もあります。成長する余地があるかどうかは検討は必要ですが無理に全ての仕入先に譲歩して接する必要はありません。
●成果が出た時は、社内外で「仕入先の貢献」を見える形で称える
トラブルとは逆で、成果が出た時にはしっかりと目に見える形として形にして返すことも大切です。
・期間表彰制度
例えば年に1回、仕入先表彰をおこなうことは有効です。
私は前職の購買部署時代には表彰の項目としては例えば以下のような表彰を行っておりました。
改善提案賞:改善提案を一番提出した「最多改善提案賞」であったり、一番改善金額効果を出した「最高改善提案賞」といったものがあります。
または提出件数と改善効果をそれぞれ順位付けして、トータルで順位決めをするという方法もあります。
品質に関する表彰:年間を通じて品質不具合がゼロの仕入先を表彰します。複数社ある場合は、発注件数が多い(分母が多い)仕入先や、発注側にとって重要な部品を発注している仕入先に加点をして順位付けするという方法もあります。
納期に関する表彰:重要な案件に対して納期短縮をおこなってくれた仕入先や、短納期対応を多くしてくれた仕入先や、重要部品の製作リードタイムを短縮した仕入先などを表彰します。
表彰には報奨金とともに盾やトロフィー、表彰などを授与します。仕入先の玄関や受付、応接室で飾っていただくことで仕入先にとっても価格、納期、品質など表彰された項目が強いのかと、プロモーションに活かしてもらうことができます。
・お礼の一言や最終結果報告
表彰制度のような大きく目に見えるような称賛も大切ですが、細やかな連絡も十分効果があります。例えば、仕入先から納入してもらった部品で製造された製品が無事に最終顧客に納入されたら、仕入先に「おかげで無事に最終顧客に納期通りに納入出来ました。顧客も非常に喜んでいただけました。この度は誠にありがとうございました。」といったように一言かけるだけで、「自分達の仕事が報われた」「自分達の仕事が多くの人のためになった」といった達成感に繋がり、今後の仕事のモチベーションや発注側への愛顧精神、信頼関係が築かれます。
■ おわりに|“信頼される発注者”という選択肢を持とう
仕入先との関係は、“安い、早い“といった目の前に見える価値だけではなく、“共に未来を創れるかどうか”で判断される時代、”選ぶ発注者”ではなく”選ばれる発注者”にいかにしてなるかの時代になってきています。仕入先のことを考えずに目先の利益や購買担当者としての傲慢や怠惰な態度や行動が仕入先を疲弊させ、また優秀な仕入先が離れていくきっかけとなり、結果的にQCD全てにおいて悪化してしまいます。優秀な仕入先との関係性が崩壊するのは一瞬ですが、パートナーシップを組み、互いに成長するには時間がかかります。
何よりも信頼関係の構築、自社ばかりではなく仕入先のことを真に考える購買が今の時代に求められるバイヤーです。