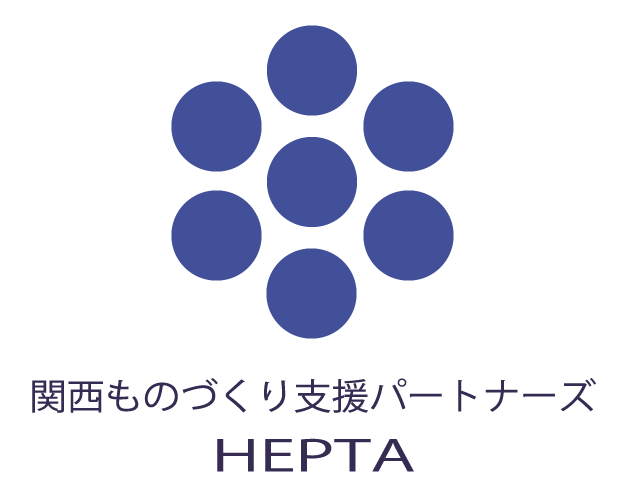こんんちは。ものづくり支援パートナーズの上村です。
前回の記事では「相見積もりだけでは弱い」という話をしました。単価の安さだけで判断すると“見えないコスト”を見落としがちだからです。今回はその延長として、「値引き交渉の落とし穴」を一つ、実例に近い形でご紹介します。
値引き後に現れた「小さな遅延」という大問題
ある製造業の社長は、取引先A社に対して「他社はもっと安い」と強めに値引き交渉を行い、見事に単価を5%下げることに成功しました。
しかしその数カ月後から、納品が微妙に遅れるようになりました。1日遅れ、ひどい時には2日。A社いわく「社内で優先順位の調整がありまして…」とのこと。つまり、値引きによって“優先されない発注先”になったわけです。
結果として工場側では在庫調整がうまく回らず、急遽短納期で材料を追加手配。一見小さな遅れですが、それによる現場の混乱と対応コストは、値引きで浮いた金額をあっという間に超えてしまいました。
値引き交渉の裏側で起きていること
値引きは確かに分かりやすい成果です。数字で表れ、社内報告もしやすい。しかし、交渉の仕方や関係性によっては、次のような“見えない反動”が発生します。
- 社内優先順位の低下(=納期や対応スピードが落ちる)
- 品質管理のラインが簡素化される(=微妙な不良が増える)
- 担当者のモチベーションが下がる(=連携の質が下がる)
値段だけ下げたつもりが、“サービス面での見えない値上げ”が起こるわけです。
「値段」ではなく「総価値」で取引を判断する視点
経営者の方にぜひ意識していただきたいのは、「値段が下がった=得をした」という単純な構図ではなく、「支払った対価に見合う価値を受け取っているか?」という視点です。
たとえば、こうした要素も含めて評価してみてください。
- 安定納期の価値 … 生産の遅れを防ぐ見えない利益
- 相談できる関係性の価値 … 急な仕様変更に対応してくれる柔軟性
- 現場対応力の価値 … 伝票や書類の修正にすぐ対応してくれるスピード感
数字に出ないこの価値こそが、中小企業にとっては“利益を守る最後の砦”になります。
値引きより「関係構築交渉」へ
もちろん全く値引きをしない方が良い、という話ではありません。問題は「値引き一辺倒になること」です。
実際に成果を出している会社は、こうした交渉をしています。
「今期は数量が増えそうなので、その分でコスト見直しできると嬉しいです」
「御社としてもメリットが出るやり方で、一緒にコストを下げられませんか?」
このスタンスだと、「値下げしてもらう」交渉ではなく、「共に効率化する」相談に変わります。結果的に、相手の協力度や優先度が落ちることはありません。
まとめ
値引きは分かりやすい成果ですが、その裏で“見えないコスト”が発生していないかを常に疑う視点が必要です。大事なのは「単価」ではなく「総価値」。サプライヤーと“敵対交渉”ではなく“共創交渉”ができる企業こそ、最終的に強い調達力を持つことになります。